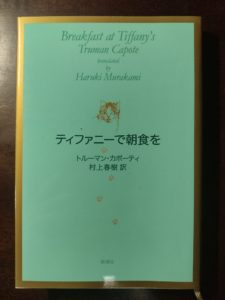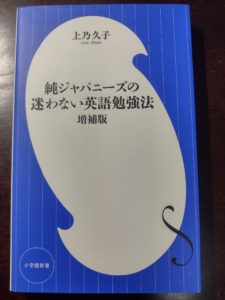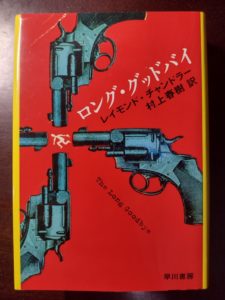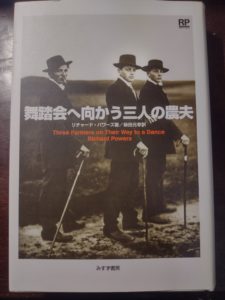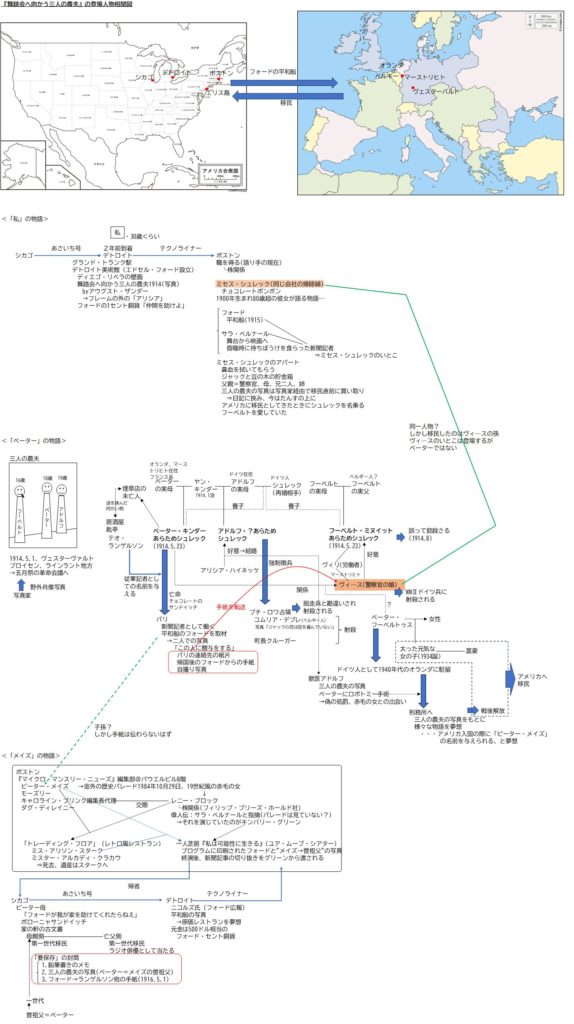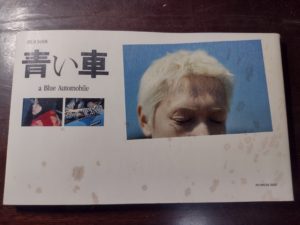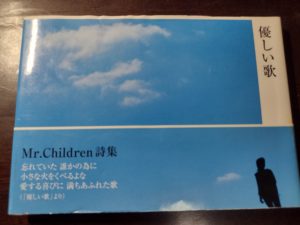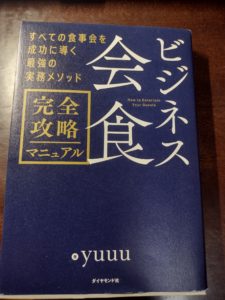
良書。コロナ禍を経ていまこういう本は現場では重宝されるのではないでしょうか。意外と会食のノウハウを体系的なまとめた本というのはなくて、ぼくも社内の暗黙知がわからなかった時代も長かったわけですが(今もそれほど得意ではない)、勉強しようと思えば今はいろいろな情報があるので本当にいいですよね。
10年前であれば『ハーバード流宴会術』という商社筋の本があって、これはノウハウ本としてはぼくもよく読んでいましたが、本書はもっと体系立っています。ただ、「マニュアル」と名乗るほどドライではない。著者の年齢はよくわかりませんが、京大院を出て広告代理店に入った苦労をもとに書かれたわりには、もうすっかり鬼のナンチャラに毒されている感じがもう端々からあって読んでいて疲れる。そういうのをもっとそぎ落とせばしっかり「マニュアル」なのにもったいない。
ぼくたちが読みたいのは具体的なノウハウであって著者の俺はすごいぞエピソードではない。なんというか京大出ても会社に入って何十年も仕事すると頭の中がこんなになっちゃうんだな、というサンプルを見せつけられているようでそれはそれでつらい。とても頭のいい人が、社会に出て、会社の暗黙知(というか会社という部族のきわめてたこつぼ的な「文化」)を言語化してくれたその「人類学者」みたいな視点があれば、もっとユーモアもあったはずなのに。あと、決定的に欠けているのは海外からのお客さんへの対処。これはこれからの時代避けて通れないと思います。
ついでに70年~80年生まれのオッサンが喜ぶカラオケリストはけっこう衝撃だ。自分が懐メロとして聞いている曲がこういう風にリストアップされて消費されるというのはなかなか居心地悪いものだ。若い人は若い曲を歌ってくれてそれを聞いて学ぶ方がオッサンにはいい機会になるんだけどな。とはいえ、そういう風に社会から見られているような年齢に自分も差しかかってしまったということは受け止めねばならないのでしょう。