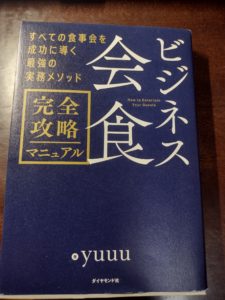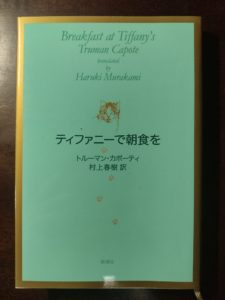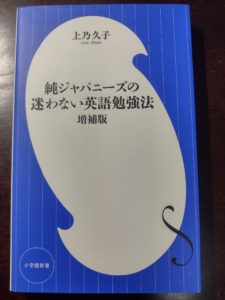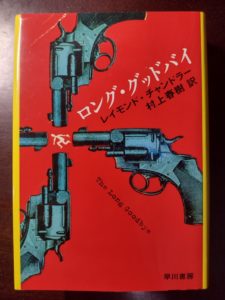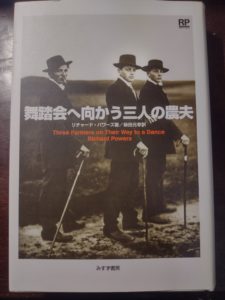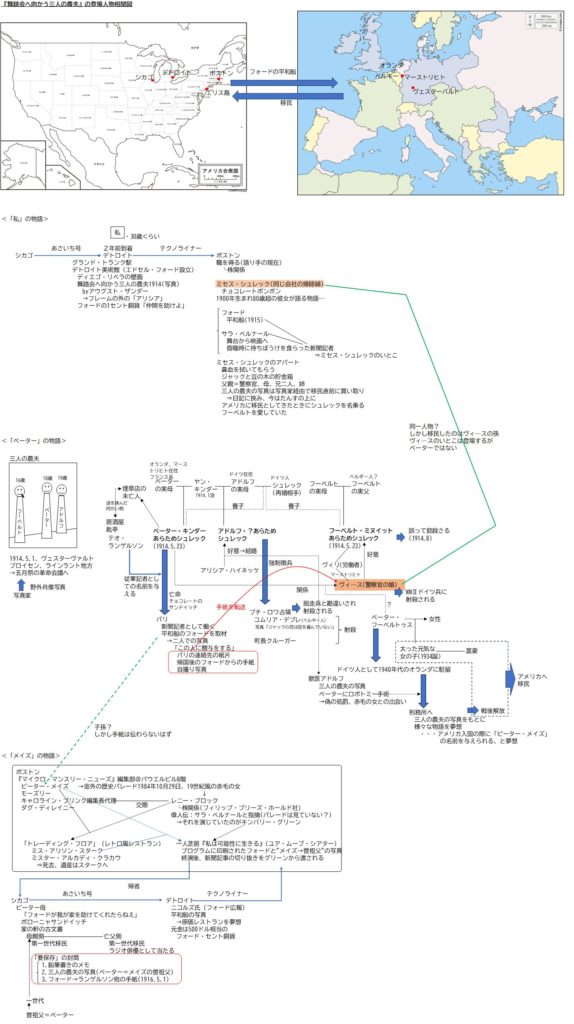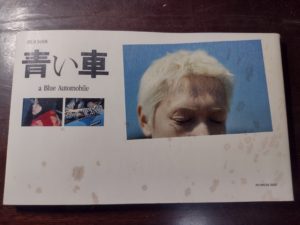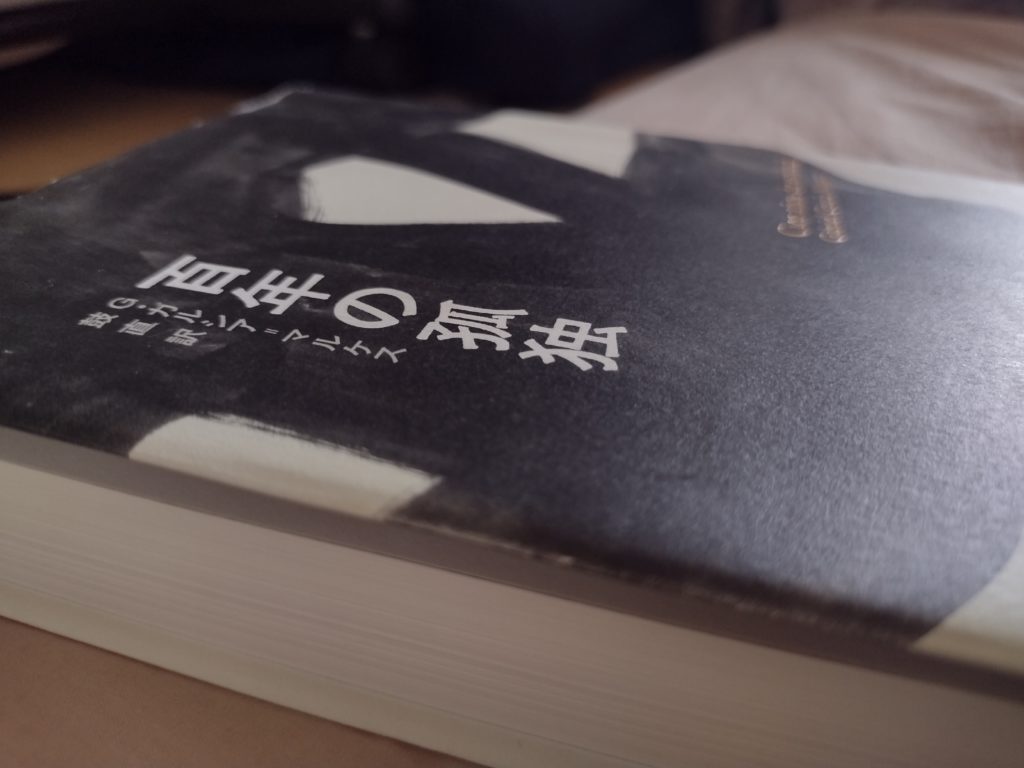
結局のところ、フィジカルな「家」の物語なんだと思います。それを通じてある一族の盛衰が語られるのですが、それは付随的なもので、やはり家が大きくなり、虫に食われ、金を隠されたと思えばひっくり返され、埋め戻され掃除され整理され、また次世代が住まう場所として再生していく。
けっして永劫回帰というか、よく言われるように同じ名前の人間がたくさん出てくるからと言って「反復」を良しとしているわけではないと思います。やはり中心にあるのはアウレリャノ大佐の放浪癖と人を引き付ける魅力、そしてウルスラの肝っ玉母ちゃん的な土に根差した母性。それらがあの世へ旅立ってしまうと、あとは結構小物キャラがうごめいているだけにも見えてしまう。でも、繰り返し出てくる「孤独」という言葉。百年の「孤独」とはなんなのか? 愛をめぐる、愛を求めるその様なのか。一族の中でいとこ同士や年齢差を越えても激しく愛し合い、そしてトリックスターとして何人も登場してくる遊女たち。しかし注目すべきはそこに優劣が無いということ。封建的な「家」制度ではなく、遊女たちによってこの「家」はかろうじて近親相関的な、自家中毒的な自滅をまぬかれている。「家」がそうさせている。