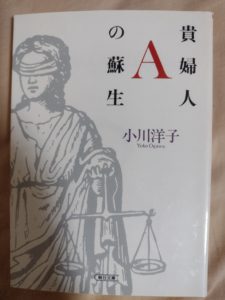小川洋子の、この恋人や親族にいわゆる「障がい者」を登場させるのはなにか作者にとってそうせずにはいられないなにか重要なモチーフなのでしょうか。もちろんそこにあまりにも「意味」を読み取ってしまうこと自体、今の時代に合わないというか、そんなことに意味を見出そうとすること自体が不謹慎だと言われかねないのでこれ以上はやめておきますが、それにしてもやはり気になってしまう。気になってしまうのは、なにかそれに対する解決や葛藤が小説のテーマにならないということ、ただそこにポンっと、「障がい」が小説世界に置かれているだけで、それをドラマの契機にしないところが作者の強い倫理なのかもしれません。もちろんこれを言うこと自体がすごく倫理的に見えてしまってやりきれないのですが。言葉にするというのは大変なことだ。
これは大学生活の最後を描いた群像劇とでも言うんでしょうか。過食症に似た症状を主人公は持ち続けているのですが、それこそ海燕つながりで吉本ばななの「キッチン」ではないが、最後に、人のために食事を作ろうとすることでなにか一つの出口が見え始める。去ってしまう恋人との食事風景は最後まで描かれない。義理の弟は食べても大きくなれない病気を患っていて、宗教団体に帰依しようとしている。それらはおそらく小説的に計算されて配置されているのでしょう。けれど、この小説は結局のところそれぞれ問題を抱えているけれど、そんなことはあたりまえで、そんな人々も大学3年から4年の最後の甘い日々=シュガータイムを過ごしていったのだ……ということでしかない。ラストシーンは食事会で終わるのではなく、ダメ出しのように野球場のシーンになっているのも、この小説が登場人物の設定の困難さを主題としているのではなく、そうやって人生は続いていくのだということにフォーカスしようとする強い意志を感じる。スタジアムに吹いている風こそが、小川洋子の持ち味に他ならない。