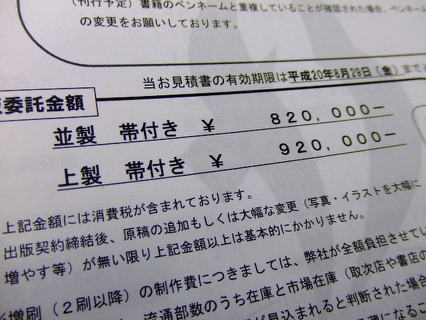谷川史子再び。コーラス系はこちらが初単行本のようです。表題作は退官間近の大学教授とその担当学生との物語。河野裕子という歌人の短歌をモチーフに作られていますが、その解釈の広がりになかなかうならせられます。淡々と自分の臆病さを文字にする、それは自己満足と呼ぶにはあまりに凛とした姿。

オノナツメも二冊目。こちらはレストランのダンディな従業員たちとそこに転がり込んだ女の子との物語。あれ、「積極」もそうだけど”おじさま萌え”みたいのってマンガの潮流として最近あるの?
絵柄は「not simple」ほど単純化された描画ではなく、だいぶ雰囲気が違います。しかしながら母娘の確執というサイドストーリーは健在。

こちらは青年誌の連載。若い夫婦の物語が七話。話としては、まあ突飛なものはないです。というかそれがこの作者の持ち味か。谷川史子のマンガには絶対に器用な人間っていうのが出てこないように思います。それぞれの不器用さやマイペースさがドラマを生んでいる。ドラマといってもそれはやはりとてもほんわかしたものなのだけど。絵は抜群にキレイ。

「間取りまんが」らしい。「暮らす」ということに焦点を当てた連作。一転して出てくる人物みんな不甲斐ない。一生懸命な不器用さというのではなくて、ただただ運が悪かったり自分で自分をコントロールし切れていない。そのあたりにイライラしてしまう人は読めないかもしれない。読み終えたときにちょっと「まあいいか、これで」と少しだけ自己肯定に浸れる。